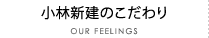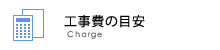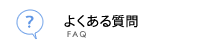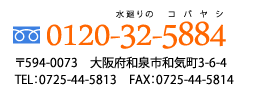スタッフブログ
お住まいについての記事、小林新建のスタッフの日常、社長ブログです。
みなさまこんにちは~(*^_^*)
以前お伝えした通り、住まいのお手入れテクニックをご紹介します!!
今回は、リビング編でございます!(^^)!
◆天井は静電気を利用してほこりを取る
→天井クロスの表面についてほこりは市販のお掃除シートやナイロン製のはたき、または不要になったパンストを
ほうきにかぶせたもので、さっとなでるようにしてとります。
隅の部分はほこりがたまりやすいので念入りにお手入れしましょう。
◆木質フロアのワックスは重ね塗りで美しく
→木質フロアの光沢がなく、くすんで見えるときはワックスをかけましょう。ワックスは乾きが遅いとほこりが
ついてしまうので、なるべく晴れた日の午前中にかけはじめましょう。
まず、部屋全体に掃除機をかけてから、洗剤拭きや水拭きをして床を綺麗にします。
その後、必ず床ワックス専用のハケやモップを使って、ワックスを木目にそって薄く
むらのないように塗ります。一度に厚く塗るよりも、表面が充分に乾いてから重ね塗りすると
綺麗に仕上がります。
◆カーペットは時々、日陰干しをして除湿
→カーペットの普段のお手入れは、掃除機で表面や裏側のほこりを丁寧にとります。
全体が汚れてきた場合は、熱めのお湯に住居用洗剤を入れ、布を浸けて固く絞り
カーペットの毛並にそって拭きます。洗剤拭きした後や、湿気の多い季節は
日陰で風通しのいい場所に干すようにしましょう。
また、掃除機で取りにくい髪の毛や糸くず、ペットの毛などは、たわしとガムテープが便利です。
◆しみ抜きは、種類によって溶剤を変える
→カーペットにシミがついたらすぐに取り除くことが大切。基本はたたくこと、水で濡らしすぎないこと。
コーヒーやジュース、しょうゆなど水溶性のしみは薄めた住居用洗剤で
クレヨン・ケチャップ・口紅など油性のものはベンジンを。
シミを取るときには、汚れが広がらないようにシミの周辺から中心に向かって拭きましょう。
◆網戸も定期的にお手入れし、きれいな窓まわりを
→網戸は、普段からブラシがけをすると汚れが抑えられます。
また、網戸の裏側に新聞紙を張って掃除機で吸い取るのも、効果的。
普段から汚れをためないようにしましょう。汚れがきになってきたら
洗剤を含ませたスポンジか雑巾を2つ用意し、網戸の両側からはさみこむようにして
汚れをふき取ります。取り外して水洗いするのが一番です。
以上、リビング編でした~!(^^)!
次回は、和室のお手入れ編をお伝えします!!
みなさま、こんにちは~(*^_^*)
最近、また一段と暑さが増してきましたね!
寝るときには、窓を全開にして蚊取り線香をつけて寝るのですが・・・
なんとも夏らしく感じております!(^^)!
ただ、昼間はかなりの暑さ・・・・汗もかなりかくので
みなさま、熱中症や脱水症状に気を付けて、しっかり水分をとってお出かけしてくださいね!!
それでは、今回は住まいのお手入れテクニックをご紹介します!
まずは・・・
外まわり編!!
◆外壁は時々水洗いして汚れを落とす
→外壁の汚れは、水をかけながら洗車用ブラシやデッキブラシで軽くこすって落とします。
キッチンの換気扇周辺などについた油汚れは、住まいの強力洗剤で落としましょう。
ただし、目立たない場所で変色しないことを確認しましょう。
◆基礎換気口はいつも風通しよく
→基礎換気口は、住まいの通風・換気の促進に欠かせません。
通風を防がないためにも、換気口の前に段ボールや鉢植えなど物を置かないようにしましょう。
また、換気口が泥などで目詰まりしているときには、洗車用ブラシで汚れを取り除くようにしましょう。
◆雨戸が傾いているときは、戸車を調整
→雨戸は普段のお手入れは、水拭きで充分です。年に1~2回、住まいの洗剤で拭いた後
水拭きし仕上げにカーワックスをかけておくと、ツヤだしと汚れ防止の効果があります。
また、レールに砂やほこりがあると、開閉時に雨戸を傷めることがあるので
レールも掃除しておきましょう。
雨戸(引き戸タイプ)を閉めて、上部または下部に隙間ができるときは、雨戸の下についている左右2個の
戸車を調整して雨戸の傾きをなおします。
◆バルコニーは普段から拭き掃除で綺麗に
→バルコニーの床には、細かいほこりや砂がたまりやすく防水面に傷をつける原因にもなりかねません。
普段からこまめに箒で掃くようにしましょう。
頑固な汚れはスポンジや洗車用ブラシに住まいの洗剤をつけてこすった後
水拭きし、最後に水分をよく拭き取っておきます。
その際は床の防水面に傷をつける金属タワシなどは使わないようにしましょう。
大量の水を流すとゴミやほこりが排水口に流れ込んで詰まる可能性があるので避けましょう。
◆門扉・フェンスの汚れにはカーワックスを活用
→門扉やフェンスは道路に面している場所だけに、ほこりっぽくなりがちです。
そのままにして汚れをためてしまうと、落としにくくなるので、こまめに布で乾拭きするようにします。
また、落ちにくい汚れはカーワックスを布につけてこすり落としましょう。
汚れ防止にもなります。
◆スチール製の門扉やフェンスは早めに塗装を
→スチール製の門扉やフェンスは表面に傷がつくと赤いサビが発生し次第には周辺に広がります。
傷がついた箇所は、早めに塗装を塗って補修するようにしましょう。
美しさや耐久性を維持するためには、3~5年位1度の塗り替えがおすすめです。
◆塀はこまめに水洗いして美しく
→コンクリートや石の塀は時々水洗いし、汚れが目立ってきたらタワシや洗車用ブラシに
住まいの洗剤をつけてこすり、水で洗い流します。コンクリートブロックは吸水性があるため
汚れを放っておくと汚れが浸透して落としにくくなるため早めにお手入れしましょう。
◆排水マスは定期的にお手入れを忘れずに
→排水マスにごみや泥などがたまっていると、スムーズには排水できず詰まる原因にもなります。
時々水を流して排水状態をチェックしましょう。また、キッチンや浴室・洗面室の
排水マスは油分やせっけんカスが付着し、汚れがたまりやすいので
定期的に掃除するようにしましょう。
◆玄関ポーチはクレンザーでお手入れ
→玄関ポーチの汚れが目立ってきたときは、水をまいてクレンザーをかけ
デッキブラシでこすります。その後クレンザーをしっかり洗い流しモップで水気を
よく拭き取ります。掃除の後は玄関に風をよく通し湿気がこもらないようにします
以上、外回り編でした~(^'^)
お役にたてましたでしょうか??
次回は、引き続き、リビング編をお届けしようとおもっております~!!
こんにちは(*^_^*)
どんどん、暑くなって夏が近づくにつれて、やはり害虫・・・気になりますよね?
そこで!ちょっとした害虫の撃退方法をお伝えしようと思います!(^^)!
◆換気
→換気のためには、窓を開けて空気の流れをよくすることが大切です。
しかし、空気の入口になる窓は全開にせず少しだけ開けるほうが空気の流れがはやくなって
効率よく換気できます。
◆雨の日に換気扇をまわしてはダメ
→湿気を取るために、なんでも換気扇と思っていませんか?
雨の日は湿気を家に入れてしまうことがあるので、逆効果です。
エアコンや除湿機などを使うといいでしょう。
◆エアコンはこまめに掃除
→湿気対策と思って、エアコンや除湿機を使うのはいいのですが、これもフィルターの掃除をきちんとしておかないと
中で増殖したカビ胞子を部屋中にまき散らすことになってしまいます。
フィルターは月1回以上は掃除をしてください。エアコンを運転する前には窓をあけ
送風運転をしてカビ胞子をとばすことと、スイッチを切る前も送風運転をして
エアコン内をよく乾燥させるのも忘れず行いましょう。
◆掃除機をかけてはダメ
→カビの発生しているところに掃除機をかけると、エアコンと同じようにカビの胞子を空気中にまき散らしています。
まずは、固く絞った雑巾で拭き掃除をしてから、掃除機をかけましょう。
※ただし、今どきの掃除機は違っています!!
現在市販されている「ヘパフィルター」がついた掃除機は、0.3ミクロンのちりまで
集塵可能です。カビの胞子は3~2ミクロンと言われていますから
カビの胞子は掃除機で取り除くことができます。
◆水槽や観葉植物もカビの発生原因
→熱帯魚・金魚などの水槽や観葉植物を置くと室内の湿度が上がってしまいます。
できれば、リビングなどの居室ではなく玄関など風通しのよいところに置きましょう。
いかがでしたでしょうか?
カビなどの不快な害虫を取り除いて快適に過ごせるよう
小さなことでも心がけていきましょう(*^_^*)
みなさま、こんにちは~(*^_^*)
毎回言っているような気もしますが、本当、この時期ってじめじめしていて
気分も晴れないですよね~(+o+)
そんな中、雨が多くなると家で過ごす時間も多くなることでしょう!
そこで、ちょっとした心がけひとつで、湿気をこもらせず
雨や曇りでも快適な住まいで生活できるような対策方法をお伝えしようと思います。
家の中に湿気がこもってしまうと、カビなどの原因になり衛生的にもよくありません。
また、家の中もべたべたしていると不快な気分になってしまいます。
◆家に湿気をこもらせない方法!!
①換気を行う
→まずは基本の「換気」
天気のいい日は2時間ほど家中の窓をあけカーテンや玄関のドアもあけて換気を行います。
また、換気の際は、クローゼット・トイレ・お風呂場などの湿気がたまりやすい場所も
すべて開け放ちましょう。
1日1回は開け放って換気するだけでも、湿気がこもらずカビ対策になります。
※天候の悪い日は、かえって湿っぽくなるので換気は控えましょう。
また、風邪の通りにくいところは扇風機を当てたり換気扇を回して風邪を通しましょう。
②なんでも乾かしてから片付ける
→キッチンの食器や玄関の傘などぬれてしまうようなものは、
必ず完全に乾かしてから片付けるようにしましょう。
③乾拭きを行う
→ぞうきんがけを行うとき、汚れを落とすためどうしても水拭きしてしまいますよね。
そのままにすると、湿気の原因になります。
ぞうきんがけをしたあとは、必ず乾いたぞうきんで乾拭きするようにしましょう。
以上いかがでしょう?
こんなに簡単な3つのことを、心がけるだけで!
過ごしやすい家がつくれるならば、、、心がけますよね!(^^)!
湿気にまけない、快適な家づくりを目指しましょう!!
みなさま、こんにちは~(*^_^*)
梅雨入りして、なんだか気分の上がらない毎日がつづきますね~
早く、梅雨あけてほしいですよね(+o+)
ところでみなさま、夏が近づいてくるにつれてついついやってしまいがちな
「湯船につからず、シャワーだけ!」っていう方、結構いるのではないでしょうか?
実は私も、シャワー派なのですが、ネットサーフィンをしていると
なんとも興味深い記事を発見(*^_^*)
なんと!!
浴槽につかるということには、夏バテ防止のヒントがあるみたいなんです!!
夏バテによる症状は、全身の疲労感・疲れやすい・無気力・立ちくらみ
めまい・食欲不振などなど・・・様々ですが
バランスのとれた食事や適度な運動などを始めるのと一緒に
今一度、入浴についてかんがてみましょう!(^^)!
◆どうしてお風呂に入ると夏バテにいいの?
ぬるめのお湯につかると、福交感神経が活発になりリラックス効果が得られぐっすり眠ることができる
◆自律神経と免疫力の関係
自律神経とは、交感神経と副交感神経をあわせた総称で、交感神経が優位に働くと
活動的な状態になり、副交感神経が働くとリラックスした状態になります。
このバランスが崩れると自律神経が乱れ、免疫力が低下ししまいます。
免疫力を低下させないよう自律神経のバランスを整える方法として入浴は見逃せません!
◆夏バテに効果的な入浴方法
リラックスするのに最適な入浴方法は、38~40度のぬるめのお湯に
20~30分つかること。
血管が広がり全身の血液循環が活発になると同時に汗をかくことで
体内の老廃物が体外に排出される。
◎入浴効果を相乗的に高める方法
□半身浴
身体のみぞおちより下だけお湯につかる方法。身体に対しての水圧が低い為心臓に負担がかからず
長時間入浴するのにむいている。また、下半身のほうが体温が低い為、その血液を全身にめぐらせるのにも効果的。
汗が出にくい人は、お風呂の前にコップ1杯程度の水分補給をし、お湯になかに
少量の塩を多さじ1~2杯いれてみると、汗の出がぐんとよくなります
□肩や首のこりには寝湯
肩や首がこっているときは、首のあたりまでお湯につかるようにしましょう。温熱の作用で首や肩の血行が
促進され、浮力によって肩の筋肉の緊張が和らぎます。また、浴槽が長い場合は
浴槽のふちに首を乗せ、首や肩に頭の重みがかからないようにする寝湯がおすすめです
□足のむくみには、温水&冷水シャワー
立ち仕事や冷房のために足が疲れたり、むくんだりしたときは
ふくらはぎにシャワーを当てよう。あくらはぎの内側に温水を1分
外側に冷水を3~5秒ほど交互にかけると血流がよくなります
他にも静かで落ち着いた音楽をかけたり、アロマオイルや入浴剤など自分好みの香りを
浴槽に入れるなど・・・リラックスの方法はたくさんあります!
1日の疲れはその日のうちにしっかりとリラックスしておきましょう(^'^)
そして、しっかりと夏バテ対策をしましょう(*^_^*)
こんにちは~(*^_^*)
今回は、お洗濯特集の最後です!!
少し、今回は文章が長くなってしまうと思うのですが是非!最後まで目を通してみてください!(^^)!
お洗濯で衣料の色合いや形がかわってしまったり、風合いが失われてしまったりしては台無しです。
トラブルの原因と予防策を知って失敗なくお洗濯しましょう!!
◆ウール製品の縮み
□トラブルの様子
袖や見頃などが縮んでサイズが小さくなった。
繊維が絡まってフェルト状になりのばそうとしても戻せない
□原因
・強い力でこすったり、もみ洗いをした
・洗濯液の温度が高かった
・弱アルカリ性洗剤を使った
□予防策・注意
・やさしく洗う(洗濯機の弱水流や手洗いコース
・水温は30℃以下にする
・洗剤は中性洗剤を使う
◆毛羽立ち・ピリング
□トラブルの様子
表面が毛羽だったり、小さな毛玉ができて光沢がなくなる
□原因
濡れた状態で強いこすり洗いやもみ洗いをした
□予防策・注意
・やさしく洗う
・洗濯機で洗うときは洗濯ネットに入れる
・柔軟仕上げをして、繊維表面をなめらかにする
※繊維が細い為、強くこすったりもみ洗いは避けましょう
◆色落ち・色あせ
①色の濃い製品
□トラブルの様子
洗濯を繰り返していくことによって色があせて、白っぽくなったり茶褐色に変色している
□原因
・水道中の塩素による色あせ
・日光による色あせ
□予防策・注意
・すすぎすぎない(2回で充分)
・色あせを防ぐ洗剤をつかう
・日陰で干す
②生成り・淡色製品
□トラブルの様子
洗濯したら生成りや淡いパステルカラーの色が白っぽくなったり色合いが変化した
□原因
洗剤に含まれる蛍光増白剤により変色した
□予防策・注意
「無けい光」の表示がある洗剤を使用する
◆色移り
□トラブルの様子
洗濯したら、赤や黒などの別の色に染まってしまった
□原因
・色が落ちる濃い色の衣料を一緒に洗った
・ポケットの中に折り紙など色がついた紙をいれたまま洗った
・洗濯液の中に長時間つけたままにした
□予防策・注意
・濃い色の衣料は単独で洗う
・お洗濯の前にポケットの中に何も入っていないか確認する
・濃い色の衣料は洗濯液中に長時間放置しない
◆洗濯じわ
□トラブルの様子
洗濯をしたらしわになっていた
□原因
・脱水時間が長すぎた
・脱水したまま洗濯槽に長時間放置した
・洗濯液の中に長時間つけたままにした
□予防策・注意
・脱水時間は短めに
・洗濯じわ軽減の洗剤を使う
・脱水がおわったらすぐに取り出して干す
以上いかがでしょうか?
あ~、こんなことよくある!なんてこと、ありませんでしたか!(^^)!??
お洗濯上手になって、お洒落をもっともっと楽しみましょう(*^_^*)
こんにちは~!(^^)!
前回お伝えした通り、困ったときの予防策パート2でございます!!
◆保管中のカビ
→カビは栄養分と湿度や温度が高いなど、一定の条件がそろったときに発生しやすくなります
□カビの発生しやすい条件とは・・・?
衣料のカビは、カビの栄養分となる体からの汚れや食べ物のシミが残った状態で
湿度が80%、温度が20~25度を超えると発生しやすくなります
□カビを防ぐ方法
①衣料の汚れやシミを取り除いてから保管しましょう
見かけは綺麗に見えますが、一度でも着用した衣料は汚れています。
必ずお洗濯やドライクリーニングをしてから保管を心がけましょう。
②衣料の湿気を取り除きましょう
・洗濯後はしっかりとした乾燥を!!
ダウンジャケットなど厚手のものは表面が乾いていても中心部がぬれている
ことがあるので注意しましょう
・クリーニングのビニールカバーは外す
クリーニングから戻ってきた衣料はビニールカバーをはずして
湿気を飛ばしてから保管しましょう
□保管場所の湿度を低く保ち、風を通すようにする
・除湿剤をつかって湿気をとる
・たんすや引出に衣料を入れすぎない
・長期間保管するときは、ときどき空気の入替を行う
◆汗じみ
→スーツやジャケットなど頻繁に洗えないものを着用するときは、汗がつくのを防ぐように工夫し
ついたら、早めに応急手当をしましょう
□着用での工夫
①下着や汗とりパッドを活用する
下着を着用したり、衣料の脇の下の部分に汗取りパッドをつけるなどして
直接汗が衣料につくのを防ぎましょう
②制汗デオドラント剤で汗をおさえましょう
わきの下などに制汗デオドラント剤をスプレーして体からでる汗を抑えておくと
たくさんの汗で服に汗じみがつくのを防ぐことができます
□着用後のお手入れ
①脱いだらすぐにお手入れをしましょう
汗が乾かないうちに対処するのがポイント
②タオルに汗を移す
水でぬらして絞ったタオル2枚を用意し汗がしみている部分をはさむように両側からおさえて
タオルに汗を移しとります。汗がしみている周辺から中心にむけて
広がらないように抑えていくのがコツです。
以上で、お洋服につく汚れなどの予防策をご紹介しました(*^_^*)
是非実践して、綺麗な衣料をいつまでも長持ちさせましょう!!
こんにちは(^'^)
今回は、お洗濯というよりか普段の生活でつく汚れを防ぐ方法をご紹介しようと思います(*^_^*)
◆泥はね・食べこぼし
→泥はねや食べこぼしは、一度ついてしまうと落とすのは一苦労。
汚れがつく前にはっ水剤をスプレーしてガードしておく。
◎はっ水剤で汚れをガード
・はっ水処理した衣料は雨や雪のほか、泥や食べこぼしもはじくので汚れを防げます
・お洗濯の後には、はっ水剤を使って撥水加工を行っておきましょう
・衣料だけでなく布製のスニーカーにもはっ水処理すると雨や泥をはじいて便利です。
※本革・人口皮革・毛皮・絹・和服には使えません
※目立たない部分でシミや白化など以上が起きないかを確かめてください
◎はっ水処理の仕方
①風通しのよい屋外で、風上から風下にかけて使用する
→はっ水剤の缶をよく振ったあと、約20cm離した位置から
しっとり濡れる程度にまんべんなくスプレーします
②風通しのよいところで、自然乾燥します
→30分程たって、完全に乾いたことを確認して終了です。
◆黒ずみ
→時間とともになんとなく黒ずんでくるカーテンやソファーカバー。
その原因は排気ガスなどに含まれる見えない微粒子が静電気で吸い寄せられたものです。
◎静電気防止剤や柔軟剤で防止
→ナイロンやポリエステルなどの化学繊維は静電気が起きやすい素材です。
静電気防止剤をスプレーしたり柔軟剤を使うとパチパチを防ぐだけでなく見えない微粒子がついて
黒ずむのを抑えることができます。
◆型崩れ
→衣料はお洗濯したり、着用したりするとしわや収縮、よれなどの型崩れを起こします。
それぞれの場面でちょっと気を使うと防げます。
◎洗うときの型崩れを防ぐ
①洗濯ネットを活用しましょう
ニットなどの、のびやすい生地やスラックスなど長くて絡みやすいものは
型崩れしやすいので、ネットに入れましょう
②乱暴に洗わないようにしましょう
毛製品や薄手の生地は乱暴に洗うと収縮したり織糸がずれて型崩れしてしまいます。
③型崩れ防止剤を使いましょう
大切にしたい衣料は、スタイル保持成分が配合されたおしゃれ着用洗剤を使いましょう
◎干すときの型崩れを防ぐ
①干す前に形をできるだけ整えましょう
②着用している形に干しましょう
◎着用での型崩れを防ぐ
①続けて毎日の着用はやめましょう
衣料は着用することで、布地がゆがみ型崩れをおこします。
布地がもとに戻るための休憩時間を与えましょう
②ぬいだら、しわ取り防臭スプレーを使いましょう
以上いかがでしょうか?
困らない為の予防策は、まだまだございます(*^_^*)
ただ、文章が長くなってしまうのでまた次回、お伝えさせて頂くので
楽しみにしておいて頂けたら幸いでございます!(^^)!
みなさま、こんにちは~!(^^)!
今回も、お洗濯の知識についてです!!
アイテム別のお洗濯のポイントをお伝えしようと思うのですがアイテムって数知れずですよね・・・
なので、定番のみなさまがよく使うであろうアイテムに絞ってお伝えしようと思います(*^_^*)
◆カットソー・Tシャツ
→デザインが多彩で、装飾品やプリントがついているものなどが増えている
◎ポイント
・型崩れを防ぐため、洗濯ネットにいれて洗います
・干す前に形を整えるようにしましょう
□洗う手順
①取扱い絵表示をみて、家庭で洗えるかどうか確認する
②適切な洗剤を選ぶ
③目立つ汚れがある場合は前処理しておきましょう
※袖口や衿などの部分汚れは、もみ洗いすると伸びるのでやめましょう
④飾りがある場合は衣料を洗濯ネットに入れます
⑤表示に従ってやさしく洗う
⑥柔軟剤仕上げをする
⑦短時間で脱水する
□干す手順
①干す前にしわを伸ばし、形を整えます
②ハンガーにかけて干します
※表面のしわは、手のひらアイロンで!!
※しわ取り防臭スプレーを使ってスタイルキープ!!
◆ワイシャツ
→お洗濯の基本アイテムです。汚れの落とし方やしわとり方法など、綺麗に見せるこつを知っておきましょう。
◎ポイント
・衿や袖の汚れは前処理します
・干す前にしわを伸ばします
□洗う手順
①取扱い絵表示を確認して洗濯方法を確かめる
②適切な洗剤を選びます
③目立つ汚れがある場合は前処理します
④洗濯ネットに入れます
※袖の絡まりや衿さきのすすれを防ぐためネットに入れましょう。
しわになrないよう、ネット1つにつきワイシャツは1枚にしておきましょう。
⑤表示に従ってやさしく洗います
⑥柔軟剤仕上げをします
⑦短時間で脱水します
□干す
①干す前に軽くしわを伸ばします
②しわ取り防臭スプレーをかけて干します
※スプレー後は、生地をななめ方向に軽く引っ張りながら、縦横や縫い目方向に引っ張り
形を整えます。衿は着用時のように立体的に形を整え、第一ボタンを整えておきます。
乾いたときは自然な張りのある仕上がりにあります。
◆ジーンズ
→ビンテージ風や刺繍の装飾がついていたり、ストレッチ素材のすきにータイプなどお洗濯に
気をつけたいデリケートなジーンズが増えています。
◎ポイント
・色落ちしやすいので単独であらいましょう。
・はきやすいように柔軟剤を使いましょう。
□洗う大田
①取扱い絵表示をみて、家庭で洗えるかどうか確認する
②適切な洗剤を選びます
③目立つ汚れがある場合は前処理します
※金属製の装飾があるものに漂白剤は使えません
④裏返しにするか、ネットに入れる
⑤表示に従ってやさしく洗います
⑥柔軟剤仕上げをします
⑦短時間で脱水します
□干す
①干す前にしわを伸ばし形を整えます
洗濯じわを防ぐため脱水後はすぐに取り出しましょう。
両手でウエスト部分をもってふりさばいてから全体を3~4つ折りにして手のひらでたたきしわを伸ばします。
②筒状に干します
ジーンズの形を保ち早く乾かすために、小物干しなどに筒状に吊るし日陰に干します。
裏側にポケットがある場合は早く乾燥させるために裏返しにして干しましょう。
以上になります!!いかがでしょうか?
まだまだ、アイテムはたくさんありますし、アイテムによってお手入れの仕方もかなり変わってきます!
大切なお洋服を大切に守れるよう、もし、こんなアイテムのお手入れが知りたい!なんてありましたら
聞いてみたくださいね~)^o^(
こんにちは~)^o^(
今回は第3弾、洗濯機で洗うポイントについてお伝えしようと思います!
洗濯機には、いろいろなコースや機能がついていますが、実際使われていますか?
衣料の種類などに合わせて効率よくお洗濯しましょう(*^_^*)
◆洗濯機で洗うポイント
◎洗濯物は入れすぎないようにする
洗濯機に表示されている洗濯物の量の7~8割程度にしておきましょう。
入れすぎると、布の動きが悪く汚れが落ちにくくなります
◎洗剤は軽量して入れます
洗濯物の量や水の量に合わせて、軽量していれます。
洗剤投入ケースを使用したり、注水のタイミングで投入するなど洗剤が
1か所にかたよらないように配慮しましょう
※直接衣料にふりかけると、溶け残りや蛍光増白剤による色むらが起きることがあります
◎柔軟剤をセットします
柔軟剤を使う場合は、洗濯の開始前に柔軟剤自動投入ケースにセットします。
すすぎの2回目に柔軟剤が投入され柔軟処理が行われます
※洗剤液の中に柔軟剤が投入されると成分が反応して互いの効果がなくなってしまいます。
直接いれる場合はすすぎの水がきれいになったときに入れます
◎衣料に適した洗濯コースを選びましょう
衣料の取り扱い絵表示や洗濯機の取り扱い説明書を確認して
適切な洗濯コースや水流を選びましょう。
◆すすぐ、脱水のポイント
◎すすぎ
1、きれいな水で行います
2、すすぎ時間を必要以上に長くすると布地を痛めます
3、すすぎに移る前に軽く脱水しておくと、泡切れがよくなります
4、柔軟剤を使うときは、すすぎの2回目に入れます
◎脱水
1、脱水のしすぎは、しわの原因になります
2、しわになりやすいレーヨンやポリエステル素材などは
脱水時間を1分以内と短めにしましょう
3、脱水が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、しわを伸ばして形を整えましょう。
以上、いかがでしょうか?
なんか、洗濯機の機能ってあまり使わずいつも「標準コース」で洗ったりしませんか?
是非是非、こういう情報を活用していきたいですよね(^_^)
こんにちは~)^o^(
今日は、さっそく前回に引き続くお洗濯知識第2弾で~す!!
洗濯を始める前に、衣料を点検し、仕分けを行ったりしていますか?
洗濯中の失敗を防ぐためには、大切なので心がけましょう(*^_^*)
■洗濯物の点検
1、鍵ホックやファスナーは閉じておきましょう
2、シミやひどい汚れの部分を確認しましょう
3、ほころびや取れそうなボタンは直しておきましょう
4、ポケットの中のものは取り出しておく
■洗い物の仕分け
ポイントは似たもの同士を洗うこと!!
1、汚れのひどいもの(汚れがほかの衣料につくのを防ぐため)
2、色落ちしやすいもの(ほかの衣料に色移りしないために)
3、毛やラグジュアリーなどデリケートなもの(やさしく洗わなければいけないから)
4、白っぽいもの、化学繊維のもの(ほかの衣料の汚れの付着を防ぐため)
5、生成りや淡白のもの(無蛍光の洗剤で洗うため)
以上、いかがでしょう?
これらのことを、しっかりと点検し、仕分けすることで大事な衣料は
守れるんですね)^o^(
私も今日から、実践してみま~す!!
みなさま、こんにちは~)^o^(
前回のお掃除に引き続き、暮らしのお役立ち情報をお伝えしようと思います!!
今回は、お洗濯についてなんですが・・・
大切なお洋服って、実際どう洗濯したら綺麗に保てるんだろう?とか
以外に知らないことって多いんですよね(*^_^*)
なので、順を追ってみなさまにお伝えしようとおもいます!!
まずは、たくさんある衣料の繊維の種類からお伝えしましょう。
■天然素材
◎綿
特徴:丈夫で濡れても強度がある。汗や水を吸いやすい
性質:洗濯や漂白が容易。乾きにくく、しわになりやすい
洗剤:弱アルカリ性洗剤
アイロン:180~210度
◎麻
特徴:強い。滑らかで冷感がある。弾性がない
性質:強い摩擦により毛羽立つ
洗剤:弱アルカリ性洗剤
◎ウール
特徴:表面にスケールがあり縮れている。吸湿性がよく撥水性がある
性質:乱暴に洗濯すると繊維が絡み合って縮む
洗剤:中性洗剤
アイロン:140~160度
◎カシミヤ
特徴:カシミヤ山羊の毛のこと。ウールよりも細くてやわらかい
性質:ニット製品は型崩れしやすい。摩擦に弱く破れや毛玉が発生しやすい
洗剤:中性洗剤
アイロン:140~160度
◎羽毛(ダウン・フェザー)
特徴:ダウンは羽軸がなく、綿毛状をしている。フェザーは羽軸がある
性質:日光に弱い。乱暴に扱うと傷みやすい
洗剤:中性洗剤
アイロン:アイロンはかけない
■合成繊維
◎ナイロン
特徴:引張強度が大きい。軽く伸縮性や弾力性がある。
性質:乾燥しやすく収縮しにくい。熱に弱く塩素や日光で黄変する
洗剤:弱アルカリ性洗剤
アイロン:80~120度
◎ポリエステル
特徴:軽くて基本的には強い。しわになりにくいが、つくと取れにくい
性質:乾きやすく型崩れしにくい。熱に弱い
洗剤:弱アルカリ性洗剤
アイロン:140~160度
いかがでしょうか?
ちなみに、これらの表記はたいてい、取扱い絵表示と一緒に表記されています。
是非、確認してみて大切な衣料が長持ちするようにしましょう!(^^)!